健康コラム君津健康センターの医師・スタッフから、
膠原病 様々な症状と検査について
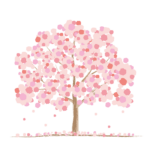
寒い冬が終わっても、なんとなく節々が痛い、だるいなどの症状はありませんか?一口に関節や体の節々が痛いといっても、一か所だけを外傷的に痛めてしまった、何もしていないのに足指の一つの関節だけが痛む、両手に左右対称の症状がある、全身の筋肉や関節に多様な症状が出ている…などなど実に様々な症状があります。そのうち複数の関節や全身に症状が出る膠原病による節々の痛みと疾患の特性、検査についてご説明したいと思います。
■ 膠原病とは
膠原病とは、皮膚、血管、筋肉などを形成するたんぱく質の一種であるコラーゲンに炎症が起きて全身の色々な臓器に病変を引き起こす病気を言います。現在、10種以上の病気が膠原病に含まれていますが、最も患者数が多いのは関節リウマチです(PICKUP参照)。関節の症状が出るので過去には整形外科で扱われることが多かったようですが、免疫の異常に由来することが分かって、内科(血液内科など)や膠原病科で診るようになってきています。
※具体的な病名:全身性エリテマトーデス(SLE)、関節リウマチ(RA)、多発性筋炎/皮膚筋炎(PM/DM)、強皮症(SSc)、シェーグレン症候群(SjS)、結節性多発動脈炎(PN)などがあります。
これらの膠原病は病気の種類によって皮膚、筋肉、複数の臓器などに特徴的な症状が現れつつ、体の様々な関節の痛みやこわばり、変形、発熱、だるさなどの全身症状は、各膠原病共通して現れやすい症状です。
膠原病は、本来は自分以外のたんぱく質に対し働くべき免疫システムが、自分の組織を攻撃してしまうことによって発生します。この何十年の治療の進歩によって多くの患者さんが日常生活を送れるようになってきましたが、治療効果が十分に得られないケースもいまだゼロにはなり切れません。
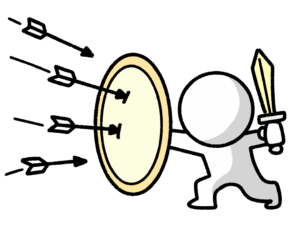
■ 膠原病を疑うべき症状
病気の種類によって異なりますが、膠原病は基本的に免疫反応やその結果として身体の中での炎症が長く続くので、発熱、だるさ、関節痛、筋肉痛などの症状が共通して認められます。また、起床時の手のこわばり、寒い場所で手指の先などがくっきりと紫色や白色に変化するレイノー現象(血管の収縮により血流が妨げられる)、色々な種類の皮疹なども膠原病でよく見られます。その他各疾患によって障害される部位は特徴的なものもあり、皮膚、筋肉、関節、神経、腎臓、血管、肺、心臓、消化管などに選択的に特有の症状が現れます。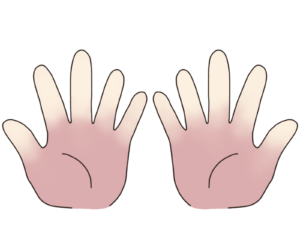
例えば、全身性エリテマトーデスの蝶形紅斑や糸球体腎炎、関節リウマチでの手指の関節変形、強皮症における皮膚硬化など特徴的な症状があります。病気の初期にはそれらの特徴はあまり目立たず、かついつから症状が出始めたかも明確にはならないことが多いため、発見が遅れることもあります。
■ 膠原病の検査と診断
膠原病が疑われる時には、症状が現れている部位や症状のタイプによって次のような検査が行われます。
➀ 血液検査・・・膠原病を引き起こす免疫系=特異的な抗体などや、体を攻撃してしまっていることによる炎症の有無は血液検査で調べられます。また、感染症など発熱や節々の痛みなどの膠原病と似た症状を起こすほかの病気ではないかどうかや、膠原病の重症度や治療効果の判定にも血液検査は有用です。(血液検査の詳細は後に別途説明します。)
➁ 画像検査・・・膠原病は、皮膚、筋肉、肺、消化管、心臓などさまざまな臓器に異常を起こす病気です。そのため、病気毎に異常の発生しやすい器官・臓器の状態をレントゲン、CT、超音波(エコー)、MRIなどの画像検査で確認します。とくに肺では膠原病に合併する間質性肺疾患が生命予後や生活のしにくさと大いに関係します。そのため、CTなど画像検査で肺の状態を確認することは非常に重要です。
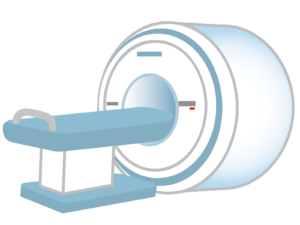
間質性肺疾患が進行すると、肺が線維化=だんだん硬くなってバリバリになり、肺胞でのガス交換がうまくいかなくなるため呼吸機能が低下して非常に苦しい思いをすることになります。一度線維化した部分は元の状態に戻ることはありません。初期は無症状でも、線維化が進行すると息切れや痰があまり絡まない咳(空咳)などが現れます。呼吸が苦しく肋間筋や横隔膜を大きく動かすため、疲れやすくなり痩せていきます。“軽い運動でも息切れがする” “坂道や階段を上るだけでも息苦しくなる”などの変化を感じたら、年齢などのせいにせず医師に相談してみましょう。間質性肺疾患の進行を防ぐためには早期発見・治療が重要です。
➂ 尿検査・・・膠原病の中には腎臓にダメージを与える病気もあります。それらの病気が疑われる場合は尿検査を行います。尿蛋白は、全身性エリテマトーデスや強皮症で腎障害があると持続的に、結節性多発動脈炎では陽性になったり陰性になったりします。血尿は全身性エリテマトーデスや結節性多発動脈炎でしばしば見られます。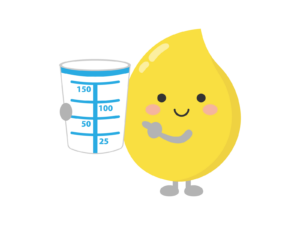

関節リウマチについて
はじめは両方の手足の指の関節が左右対称に腫れ、とくに起床時にこわばりが目立つようになります。起きて少し動かしているうちに動かしやすくなってくるのが特徴です。また、人によっては膝関節や股関節など大きな関節にも変化がおよび、水が溜まり、動きにくくなり、痛みで日常生活が困難となります。年月が経つうちに関節の破壊が進み、固まったり変形したりします。特に30~40歳代の女性に多く発症し、軽症~重症まで症状の程度は個人差が大きく、早めの診断・治療が予後に影響します。
関節リウマチは関節だけに関する疾患ではなく自己免疫疾患と考えられています。つまり、自分の身体の一部を自分ではないと誤認し、抗体をつくって反応をおこしてしまう疾患です。そのため全身の関節で関節液をつくる滑膜という組織にリンパ系の免疫細胞が集まって炎症を起こします。そのような免疫の疾患なので、貧血症状がでたり、体がだるくなったり、微熱がでるなど全身で症状が発生します。関節リウマチは診断基準に則って診断されます。基準は、5項目の臨床症状と血清リウマトイド因子、レントゲン写真上の変化の7項目からなり、そのうちの4項目以上が当てはまる場合、関節リウマチと診断します。(臨床症状は6週間以上持続していること)「血清リウマトイド因子(血液検査による)が陽性」というのは、診断基準の一つの項目が当てはまっているだけなので、この結果だけで関節リウマチということにはなりません。
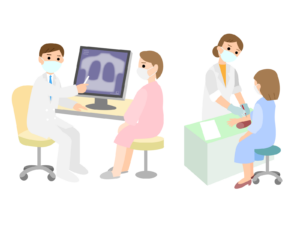
■ 血液検査について
膠原病の診断や治療において、血液検査はとても重要です。膠原病を疑った場合、レントゲンやエコーなどの画像検査に加えて、それぞれ疑う疾患にあった血液検査を行うことで、診断するための重要な情報を得られます。当センターで実施可能な血液検査の項目を抜粋し説明いたします。※健診コースによって実施できない場合もあります。お問い合わせください。

➀ リウマチ因子(RF)
リウマチ因子(RF):この数値が高いと「もしかして関節リウマチにかかっているのだろうか」と不安になるかもしれませんが、健康なひとでもリウマチ因子が陽性の方はいらっしゃいます。人口の0.5-1.0%がリウマチを発症しますが、リウマチ因子陽性確率は人口の5%以上とも言われています。皆さんが想像する以上に多いかもしれませんね。したがってこれが陽性であったとしても関節リウマチにかかっているとは限らないのです。ですのでリウマチ因子が陽性でも人生で関節リウマチになる確率が少し高いかも程度であり、現状で関節のはれや痛み、変形などの症状が無いのであれば基本的には問題ありません。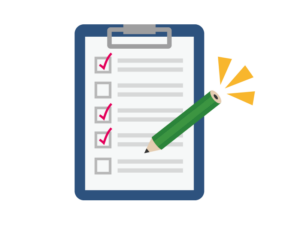
➁ CRP、血算、肝機能
CRP:膠原病の診療において、もっとも測定される項目の一つです。特に関節リウマチの治療中の患者さんにおいては治療効果判定や感染症の可能性の有無、などに有用です。患者さんの状態にもよりますが、関節リウマチで通院する患者さんのほとんどは定期的にCRPを測定します。CRPは関節炎の存在に敏感に反応します。一方で、変形性関節症(年齢などの影響で関節が変形して起こる関節症)ではCRPは上昇しません。ただし、若い方では関節リウマチでもCRPがあまり上昇しない場合もあり、注意が必要です。関節炎だけでなく、肺炎、膵炎、腸炎など炎症の名の付くものでは基本的にCRPは上昇しますので、関節炎が無いのに上昇する場合は感染症の存在などに注意する必要があります。
血算:白血球や赤血球の数やHb(ヘモグロビン、血色素)、血小板(出血を止める)の数値で、膠原病ではここでも変化が起こります。白血球や血小板が増加する疾患は、結節性多発動脈炎(PN)、関節リウマチ(RA)など。逆に白血球が減少する疾患は、全身性エリテマトーデス、シェーングレン症候群などです。全身性エリテマトーデスでは血小板も減少します。また、多くの膠原病では貧血(Hb低値)を認めます。
肝機能:その他、肝機能障害を表す数値のいくつか(AST、LDH、CK)は、筋肉が壊れても血中に増える酵素であるため、肝障害がなくても多発性筋炎/皮膚筋炎では数値が上昇するのが重要な所見です。またこれについては過剰な筋トレなどでも高値となります。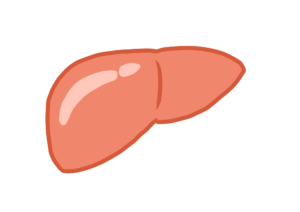
参考:医療機関受診などでの血液検査項目について 
- 抗CCP抗体(ACPA):抗CCP抗体は関節リウマチで陽性の人が多く、診断における重要な特異的自己抗体と考えられています。そのため、抗CCP抗体が陽性の場合のほうがリウマチ因子(RF)陽性よりも関節リウマチであることが多いのです。また、この抗体の数値が非常に高い患者さんの場合には関節が急速に壊されていくことが多いので、その場合よりしっかりと治療を実施することになります。とはいえ関節リウマチに罹患していてもこの抗体が陰性であるケースも10~20%見られるため、陰性だからと言って関節リウマチを完全に否定することはできません。ただし先に挙げたリウマチ因子よりは特異性が高いため、重要な検査といえます。
- 抗核抗体:若い女性に関節症状がある場合、関節リウマチ以外の病気も考える必要があります。抗核抗体が陽性になる病気には全身性エリテマトーデスのほかに、シェーグレン症候群、強皮症、多発性筋炎・皮膚筋炎などがあります。この抗核抗体は40倍、80倍、160倍、などの数値であらわされ、40倍以上を陽性と判定します。ただし、健康な人でも40倍=陽性となる場合もあり、かつ年齢とともに抗核抗体の陽性率は上昇します。そのため先に挙げたリウマチ因子(RF)と同様、抗核抗体が陽性であっても、「陽性すなわち膠原病」と即、判断することはできません。
- 抗DNA抗体:この抗体は全身性エリテマトーデスの患者さんで多く見られます。この検査でも時々膠原病とは無関係にこれらの抗体が陽性になることがあります。そこであらためて確認するために放射性免疫検出法(RIA法)と呼ばれる検査を追加で行うことがあります。全身性エリテマトーデスの診断にはこの抗体をはじめとして、いくつかの検査が必要で、やはりこの場合も症状と検査の結果をもとに、総合的に診断することになります。
- 抗SS-A抗体、抗SS-B抗体:この抗体はシェーグレン症候群の患者さんに多く認められますが、全身性エリテマトーデスや関節リウマチの患者さんでも検出されることがあります。シェーグレン症候群は涙や唾液の分泌が悪くなり、ドライアイやドライマウスを引き起こす膠原病です。この抗体は自己抗体の一つですが、抗核抗体が陰性の場合でも陽性になりえます。この抗体が陽性かつドライアイやドライマウスがある場合、シェーグレン症候群を強く疑うことになります。ドライアイやドライマウスの判断を要するので眼科など他科の医師と協力する必要があります。また、この抗体が陽性の方が妊娠した場合、赤ちゃんに不整脈などの症状が出ることがあります。産婦人科の医師にこれらの抗体が出ていることを事前にお伝えすることが重要です。
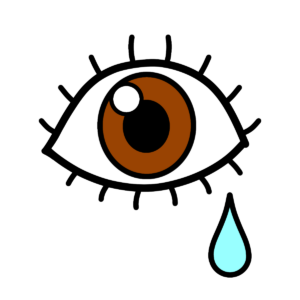
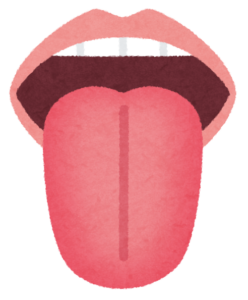

![]()
さて、節々の痛みや体全体の不調から気づかれる膠原病と、その症状や各検査項目などについてご説明してきましたが、いかがでしょうか?体の一部のみの症状(左右差ありなど)で体の動きや向きによって症状の変化があるようであれば、整形外科的な疾患が予想されます。一方、全身状態の変化を伴っている場合や、左右対称に症状が出現している場合などは内科疾患も考えられます。もし関節などの症状とともにこれらの数値が高いのだが…という方は、ぜひ健診結果をもって内科を受診し、医師の意見を聞いてみるといいでしょう。

「健康さんぽ106号」
※一般財団法人君津健康センターの許可なく転載することはご遠慮下さい。




