- 一般健康診断判定区分
- 特殊健康診断判定区分(騒音、じん肺以外)
- 騒音健康診断判定区分
- じん肺健康診断判定区分
- BMI(体格指数)
- 腹囲
- 聴力
- 血圧
- 尿素窒素・クレアチニン eGFR
- 尿酸
- 尿蛋白・潜血
- 糖代謝
- 血液一般
- 肝機能
- 脂質
- 心電図
- 眼底
- 眼圧
- 胸部X線
- 腹部超音波検査
- 便潜血(大腸がん検診)
- 胃部X線
- ABC検診判定基準
- 特定健康診査
- メタボリックシンドロームとは
- メタボリックシンドロームの診断基準
- 特定保健指導とは
健康診断結果の判定区分と項目別の見方
異常所見を見落とさずに、必要に応じて再検査や受診勧奨を行うためには、健康診断結果の判定区分の見方について知っておくことが重要です。 下記では、健康診断結果のコードおよび判定区分と各項目の内容(コメント)について説明いたします。
 健康診断の判定区分について
健康診断の判定区分について
健康診断の判定区分は健康診断の種類により異なります。結果通知書の健康診断種類(管理健診除く)を確認し下表をご参照ください。
| 一般健康診断判定区分 | ||
|---|---|---|
| コード | 判定区分 | コメント |
| N | 所見なし | 今回の検査では異常を認めません。 今後も健康増進に心がけてください。 |
| NF | 所見なし 治療継続 |
今回の検査では異常を認めません。 現在の疾患については主治医の指示通り治療を継続してください。 |
| A | わずかな所見 | わずかに所見を認めますが日常生活に支障はないでしょう。 今後も健康増進に心がけてください。 |
| AF | わずかな所見 治療継続 |
今わずかに所見を認めますが日常生活に支障はないでしょう。 現在の疾患については主治医の指示通り治療を継続してください。 |
| B | 軽度所見あり 経過観察 |
所見を認めます。 日常生活に注意し、定期的に検査を受け経過を観察してください。 |
| BF | 軽度所見あり 治療継続 |
所見を認めます。 日常生活に注意し経過を観察するとともに現在の治療を継続してください。 |
| C | 要再検査 | 念のため、もう一度同じ検査を受ける必要があります。 |
| CF | 要再検査 治療継続 |
念のため、もう一度同じ検査を受ける必要があります。 現在の疾患については主治医の指示通り治療を継続してください。 |
| D | 異常所見あり 要精密検査 |
異常所見が認められます。 疾患の存在が疑われますので、医療機関で精密検査をお受けください。 |
| DF | 異常所見あり 要精検・治療継続 |
異常所見が認められます。 医師と相談し、疾患の治療・精密検査など指示に従ってください。 |
| E | 明らかな異常所見 要 治 療 |
明らかな異常所見が認められます。 疾患の治療のため医療機関を受診し、医師の指示に従ってください。 |
| EF | 明らかな異常所見 要治療継続 |
明らかな異常所見が認められます。 医師と相談し、疾患の治療など指示に従ってください。 |
| F | 治療継続 | 現在の疾患について治療を継続してください。 |
| 特殊健康診断判定区分(騒音、じん肺以外) | ||
|---|---|---|
| コード | 管理区分 | 措 置 内 容 |
| A | 管理A | 異常なし |
| B | 管理B | 軽度異常(または疑い)(定期検査または必要に応じて就業制限) |
| C | 管理C | 異常所見有り(就業禁止および療養) |
| R | 管理R | 当該業務に就業することによる増悪の恐れのある疾病有り (就業制限、疾病の療養) |
| T | 管理T | 当該業務以外の原因による疾病または異常有り (疾病に対する療養) |
| 騒音健康診断判定区分 | ||
|---|---|---|
| コード | 管理区分 | 措 置 内 容 |
| A | 管理A | 異常なし |
| B1 | 管理B1 | 要観察者(前駆期の症状が認められる者) |
| B2 | 管理B2 | 要観察者(軽度の聴力低下が認められる者) |
| C | 管理C | 要管理者(中等度以上の聴力低下が認められる者) |
| T | 管理T | 当該業務以外の原因による疾病または異常有り (疾病に対する療養) |
| じん肺健康診断判定区分 | ||
|---|---|---|
| 管理区分 | 措 置 内 容 | |
| 管理1 | 異常なし | |
| 管理2 | 軽度所見有り | |
| 管理3イ | 中等度所見有り | |
| 管理3ロ | 中等度所見有り(軽作業転換) | |
| 管理4 | 重度所見あり(要休業療養) | |
| 管理2または3で合併症 | 合併症あり(要休業療養) | |
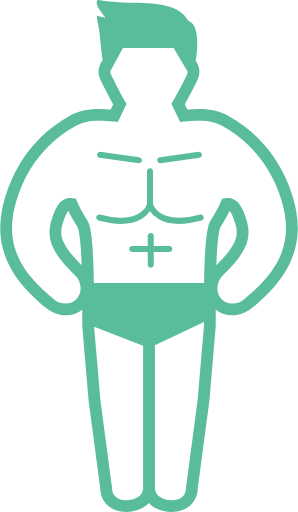 BMI(体格指数)
BMI(体格指数)
BMIは肥満の程度をあらわす指標です。
BMI = 体重(kg) ÷ 身長(m)²
BMIの標準は「22」でこの値にあたる体重を標準体重、その範囲は18.5~24.9です。
 腹囲
腹囲
内臓脂肪症候群(メタボリックシンドローム)の基準の一つです。臍高で測定を行い、男性85cm以上、女性90cm以上は腹部CT検査上の100cm²に相当し、内臓脂肪の蓄積が推測されます。
 聴力
聴力
聴力の低下の有無をみるためのスクリーニング検査です。選別聴力検査は、1,000Hz(ヘルツ)、4,000Hzの2種類の音(周波数)で検査します。 1,000Hzは、日常会話の聴力能力をみます。4,000Hzは、難聴傾向の早期発見のために行います。
 血圧
血圧
心臓から血液を送り出すとき、血管に加わる圧力を血圧といいます。心臓が収縮している時が最高(収縮期)血圧、拡張している時が最低(拡張期)血圧です。血圧が高いと、心疾患や脳血管障害の発生する危険性が高くなります。
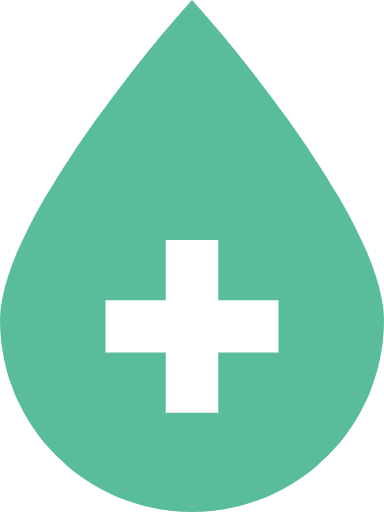 尿素窒素・クレアチニン eGFR
尿素窒素・クレアチニン eGFR
体内でたんぱく質が使われてできる物質で、腎臓から体外に排出されます。筋肉量が多いほどその量も多くなるため、基準値に男女差があります。腎機能が悪くなると排泄されず血液中に残ってしまい値が高くなるため、腎機能の目安になります。
クレアチニン・性別・年齢をもとに算出したeGFR(推算糸球体濾過量)で腎機能を評価します。
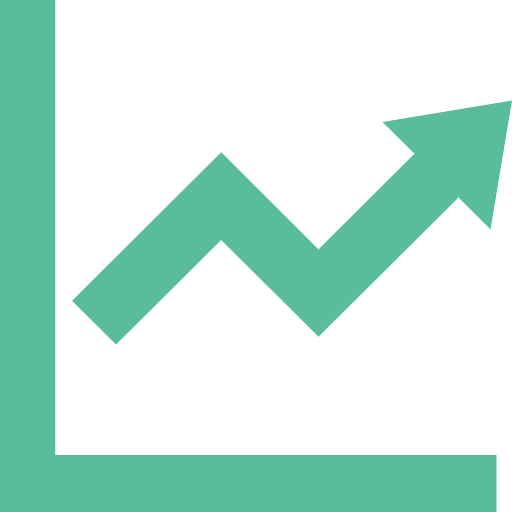 尿 酸
尿 酸
痛風の原因になる物質で、血液中の尿酸値が一定以上になると関節や腱に尿酸の結晶がたまり痛風発作を起こします。尿酸が長く高いままだと、腎障害の原因になったり、尿路結石の原因にもなります。肥満・アルコールの飲みすぎ・脱水などで高い値をとります。
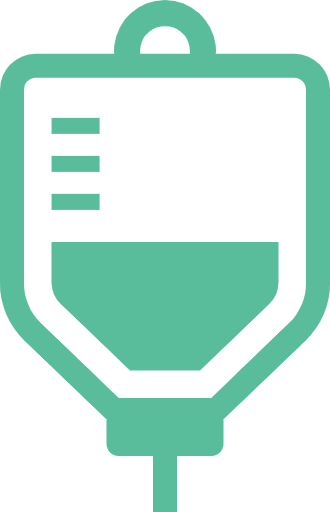 尿蛋白・潜血
尿蛋白・潜血
腎臓を含む尿路系のいずれかに異常があると、陽性になります。しかし、蛋白は運動のなど健康な人や、潜血は生理前後の女性や健康な人でも陽性になる場合もあります。陽性の場合は、精密検査が必要になることがあります。
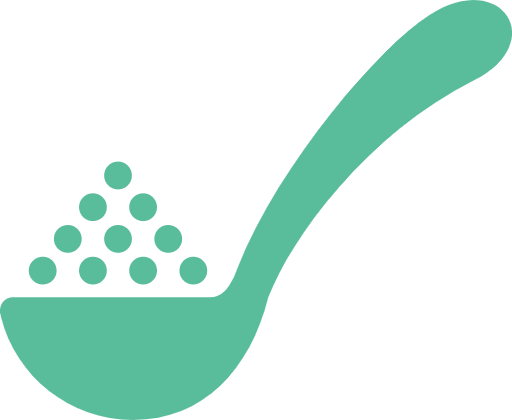 糖 代 謝
糖 代 謝
尿糖、血糖、HbA1cは糖尿病のスクリーニング検査です。糖尿病は、自覚症状が乏しい疾患で、定期的な受診が大切です。HbA1cの検査は、過去1~2ヶ月間の平均血糖レベルを示しています。糖尿病が進行すると腎臓、血管系、眼、神経系等の病気を併発します。
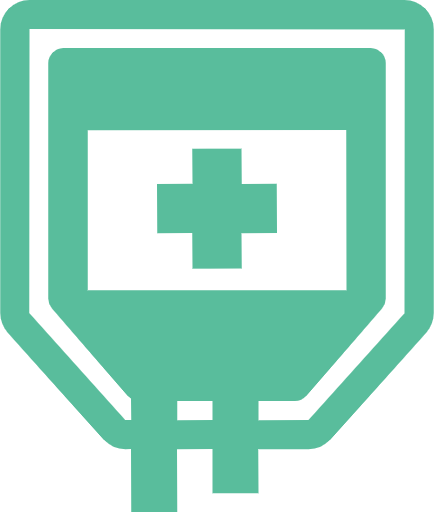 血液一般
血液一般
赤血球数、ヘモグロビン、ヘマトクリットは貧血の検査で、基準値を下回ると貧血が疑われます。 白血球数は感染症や血液疾患が疑われる場合、ヘビースモーカーでは多めの値がみられます。 血小板数は血液疾患や肝臓病が疑われる場合に値が増減します。
 肝 機 能
肝 機 能
GOT(AST)は心臓・筋肉・肝臓に多く存在する酵素で、GPT(ALT)は肝臓に多く存在する酵素です。数値が高い場合は急性肝炎・慢性肝炎・脂肪肝・アルコール性肝炎などが疑われ、GOTのみ高い場合は心筋梗塞・筋肉疾患などが疑われます。
γ-GTP(γ-GT)は、肝臓や胆道に異常があると血液中の数値が上昇します。数値が高い場合、アルコール性肝障害・慢性肝炎・胆汁うっ滞・薬物性肝障害が疑われます。
γ-GTPは2024年4月から、測定方法の見直しにより基準値が変更となります。
 脂 質
脂 質
中性脂肪はエネルギーの蓄え、コレステロールは細胞やホルモンの原料です。HDL(善玉)コレステロールはLDL(悪玉)コレステロールを取り除く働きがあります。体質・過食・運動不足・肥満によりこれらが異常値を示す状態(脂質異常症)が続くと、動脈硬化が進み、脳卒中や心臓病などの危険因子となります。
non HDLコレステロールは、中性脂肪が400mg/dl 以上の場合や食後採血時の指標として使われます。
nonHDL – C = 総コレステロール – HDLコレステロール
2024年4月から中性脂肪は、食後経過時間によって空腹時中性脂肪または随時中性脂肪に区分されます。(2024年3月以前の中性脂肪は、すべて空腹時中性脂肪で表示されます。)
 心 電 図
心 電 図
心電図は心臓のはたらきをみる検査です。不整脈(脈の乱れ)、虚血(血流が悪い状態)、刺激伝導異常(電気刺激が心臓各部に正常に伝わらない状態)などの情報が得られます。
 眼 底
眼 底
眼底撮影は、眼底の血管や網膜などの異常を見つけます。動脈硬化や高血圧、糖尿病による眼底の変化、血管からの出血状態、さらに緑内障などの眼科疾患もみることができます。
 眼 圧
眼 圧
眼球の中は房水という液体で圧力が保たれています。眼圧が低いと網膜剥離・外傷などが、高いと高眼圧症・緑内障が疑われます。
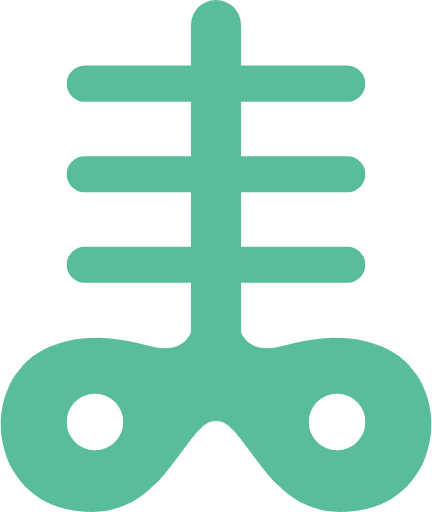 胸部X線
胸部X線
左右の肺やその間にある心臓、縦隔などの病気、例えば肺がん、肺炎、肺結核、縦隔腫瘍や心拡大などの有無を調べます。
 腹部超音波検査
腹部超音波検査
肝臓・すい臓・腎臓に腫瘍があるか、胆のうに胆石などがあるかを調べます。超音波が入りにくい部分があるため、全域を観察できないことがあります。
 便潜血(大腸がん検診)
便潜血(大腸がん検診)
消化管からの出血を調べます。出血があった場合には、炎症、潰瘍、ポリープ、がんなどが考えられます。陽性の場合は必ず大腸内視鏡検査等精密検査を受けてください。
 胃部X線
胃部X線
胃・十二指腸の病気(炎症、潰瘍、ポリープ、がんなど)の有無を調べます。
 ABC検診判定基準
ABC検診判定基準
| ABC検診 | ヘリコバクター・ピロリ抗体検査 | ||
| 陰性 (-) | 陽性 (+) | ||
| ペプシノゲン検査 | 陰性 (-) (±) | A群 | B群 |
| 陽性 (+) (2+) | C群 | ||
| A群 | ピロリ菌感染・胃粘膜萎縮ともに認められません。 |
| B群 | ピロリ菌に感染しています。消化性潰瘍・胃がんのリスクがあるため、除菌治療をお勧めします。 |
| C群 | 胃粘膜の萎縮が強く、消化性潰瘍・胃がんのリスクが高い状態です。除菌治療を行うとともに、定期的な胃内視鏡検査が必要です。 |
| E群 | ピロリ菌の除菌治療後です。主治医のもと定期的に胃内視鏡検査を受けてください。 |
 特定健康診査
特定健康診査
「高齢者の医療の確保に関する法律」のさだめにより、40歳から74歳の医療保険加入者および扶養者を対象として、【内臓脂肪型肥満】に着目した検査項目で、平成20年度から計画的に実施される健診が特定健康診査です。 定期健康診断に特定健康診査を併用して実施される場合があります。
-
- ・特定健康診査必須項目に●を表示
- ・メタボリックシンドローム判定
 メタボリックシンドロームとは
メタボリックシンドロームとは
内臓脂肪の蓄積により、脂肪細胞から高血糖・脂質異常・高血圧を引き起こすホルモンが分泌され、その結果動脈硬化が促進されて脳卒中・心疾患や糖尿病合併症などが起こってくることです。
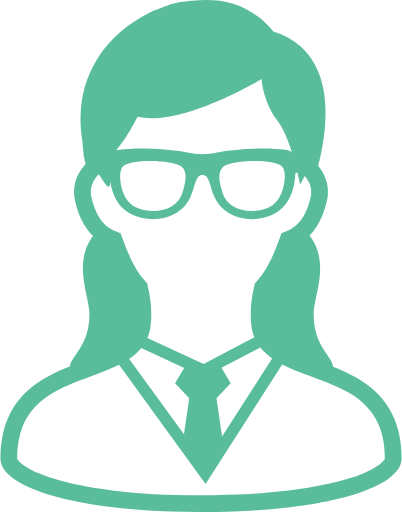 メタボリックシンドロームの診断基準
メタボリックシンドロームの診断基準
8学会策定新基準(2005年4月)
① 肥満
内臓脂肪蓄積(腹囲)
男性:85cm以上 女性:90cm以上
(内臓脂肪面積 男女ともに100cm²に相当)
+
下記2項目以上あてはまると「該当」となります
② 脂質
空腹時中性脂肪:150㎎/dl以上 または HDLコレステロール:40㎎/dl未満
(随時中性脂肪)または 服薬治療中
③ 血圧
収縮期血圧:130㎜Hg以上 または 拡張期血圧:85㎜Hg以上
または 服薬治療中
④ 血糖
空腹時血糖:110㎎/dl以上 または HbA1c:6.0%以上
または 服薬治療中
| 基準該当 | ①にあてはまり、②、③、④のうち2つ以上あてはまる場合、メタボリックシンドローム該当 |
| 予備群該当 | ①にあてはまり、②、③、④のうち1つ以上あてはまる場合、メタボリックシンドローム予備群 |
| 非該当 | 基準該当、予備群該当以外の場合、メタボリックシンドローム非該当 |
| 判定不能 | ①、②、③、④の検査項目のうち、判定を確定するために必要な項目の欠損がある場合 |
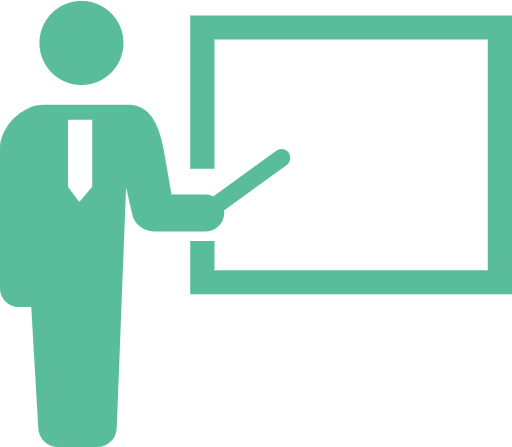 特定保健指導とは
特定保健指導とは
特定健康診査により、健康の保持に努める必要がある方に対し、計画的に医療保険者により実施される「動機づけ支援」「積極的支援」のことをいいます。





